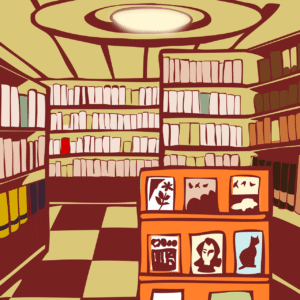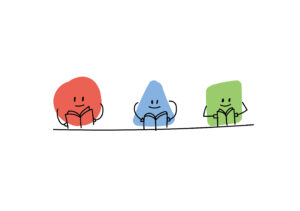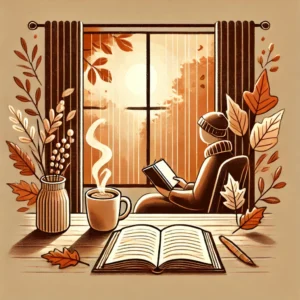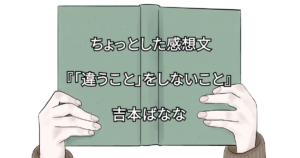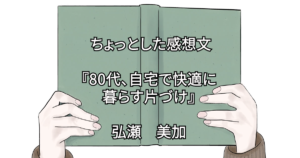「叱る」が当たり前だった時代
思い返せば、私が中学・高校の頃(25年以上前)でさえも、運動部は昭和の体育会系の名残がありました。
今でこそ減ってはきているようですが、1995年~1999年前後でも、当時は先生に平手打ちされることもありました。
もちろん、自分にも非があったりもしましたが、あの時の記憶は何十年経っても消えず、ただ嫌な思い出として残っています。何度思い出しても、めちゃくちゃこわかったな‥しかない。
それは社会人になっても似たような環境は続きました。新卒で入った会社はいわゆるブラック企業。オフィスに罵声が飛び交い、あえなく2か月でリタイアを申請するも、逃がしてもらえず、関連会社に異動になっても日々叱責の繰り返し…。今思えば、本当に辛い日々でした。
叱られている時間は、ただひたすらに「もうやめて」とだけ祈ってやりすごし、叱られたことでポジティブになったことは結局何十年経っても、ゼロと断言できます。
叱ることで評価される風潮の気持ち悪さ
そんな経験を経て、「あのとき自分を叱った先生や上司は、どんな気持ちだったのだろう」と考えるようになりました。
特に気持ち悪く感じるのは、指導者が「叱れないと評価が低い」という風潮や先入観。
もやもやした時に読んだ、村中直人さんの「〈叱る依存〉がとまらない」に書かれていた「叱る」の定義はこうでした。
言葉を用いてネガティブな感情体験(恐怖、不安、苦痛、悲しみなどを)与えることで、相手の行動や認識の変化を引き起こし、思うようにコントロールしようとする行為
村中直人「〈叱る依存〉がとまらない」
自分の選ぶ「叱らない」道
あぁ。この定義を音読すると、私は今後も、誰も叱れないなと思います。感情をぶつけるような指導は、相手の成長を妨げるだけだと感じるからです。ほかの方法を選びたい。
もちろん、間違いや改善点は伝えますが、それは冷静なフィードバックとして。つい叱っては後悔し、また繰り返してしまう——そんな経験がある方は、ぜひ一度立ち止まって、この「叱る」の定義を声に出して読んでみてほしい。
叱る依存から離れて、互いに成長できる関係を築く方が、ずっと健全で、そして長続きするんですよね。
おしまい≡⊂( ^-^)⊃♫